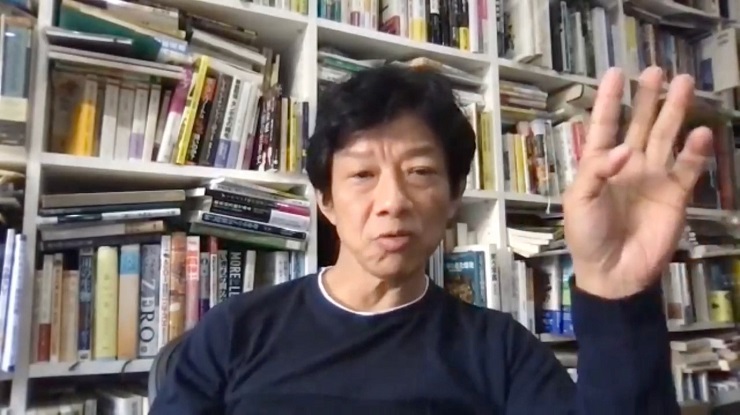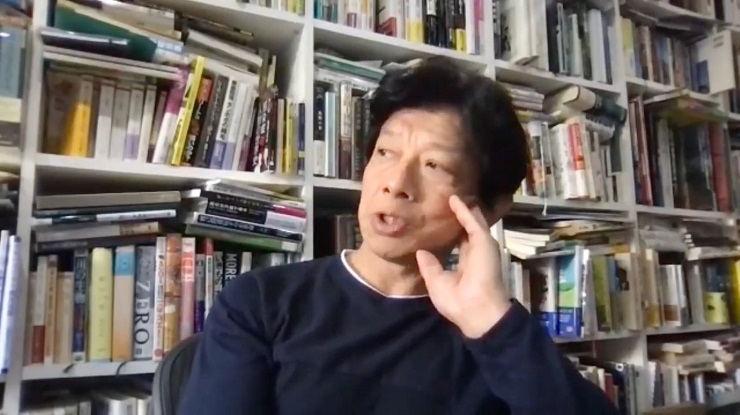人々のメディア的欲望の究極は「時空の支配」 東京工業大学教授・柳瀬博一氏が提起する日本のチャンス

メディア環境研究所は、テクノロジーの発展が生活者や社会経済に及ぼす影響を洞察することを通して、メディア環境の未来の姿を研究しています。少子化・超高齢化社会が到来する中、本プロジェクトは現在各地で開発が進められているテクノロジーの盛衰が明らかになるであろう2040年を念頭に置き、各分野の有識者が考え、実現を目指す未来の姿についてインタビューを重ねてきました。
「メディア」は世界とどう関わり、どう変えていくのでしょうか。日経BP社で30年間メディアビジネスに携わったのち、現在は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の教授(メディア論)を務める柳瀬博一さんに、メディアの進む方向性と日本の街や地域のあり方について伺いました。

私たちは「誰でもマスメディア時代」を生きている
――はじめに自己紹介を兼ねて、柳瀬さんの取り組みや関心領域を教えてください。
日経BP社で30年間、メディアの仕事をしていました。「日経ビジネス」記者や新雑誌の開発などを経験した後、書籍セクションの立ち上げメンバーとして加入し、13年間所属。また、2006年にスタートした日経ビジネスオンラインの開発チームにも加わりました。日本のネットメディアでコンテンツを広告モデルとして戦略的に活用した実例をいくつか作らせていただきました。
2018年から、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の教授になりました。僕は学者や研究者ではなく、メディアで取材し、新しいメディアを実際に作ってきた当事者なので、大学では、メディアとは一体何か? メディアとは具体的にどうやってできているかということを理工系の学生に教えています。
授業では、学生たちに「メディアは8割が理工系の仕事だ」と伝えることが多いですね。あらゆるメディアは、再生装置としてのハードウェア、伝えるコンテンツ、それを流通させるプラットフォームの三層構造でできています。コンテンツだけがメディアだと勘違いしている方もいますが、それはメディアの一部にすぎません。新聞紙、テレビ受信機、PCやスマホなどのハードウェア、記事や番組などのコンテンツを流すプラットフォームなど、理工系の技術があってはじめて、メディアは成立します。
現在、世界の企業時価総額ランキングの上位はGAFAMやテンセントなどテクノロジーを駆使した広義の意味での「メディア企業」です。30年前は日本の金融機関が上位を占めていましたが、今や見る影もありません。メディアこそ理工系のひとが活躍する舞台なのに、日本のメディア業界の多くが理工系の知恵を重視しなかったこと、インターネット時代にあらゆる仕事がテクノロジーによってメディア化する変化に気づかなかった人が多かったことが原因でしょう。
東工大の学生には「新聞記者やテレビの番組制作者以上に、iPhoneや通信技術の開発者こそがメディアを支える人たちだ」と言っています。また、彼らの多くは研究者や技術者になり、情報を発信することになります。つまり「君たちが将来就く仕事自体がメディアだ」とも伝えています。「だれでもマスメディア時代」が授業のキーワードです。
メディアの究極の欲望は人間がどこまで「時空の支配」をできるか
――身体や心の居場所など、20年後の人間の生活はどう変化していると思われますか?
まず、20年後どころか200年後も2000年後も人間という生き物自体はおそらくほとんど変化しません。1万年前のご先祖さまと私たちに差はほとんどないはずです。変化するのは文明、なかでもテクノロジーです。
僕は『ドラえもん』を世界最高峰のSFだと思っているのですが、もともと1960年代後半から70年代が舞台です。漫画の中の生活パターンはさして今と変わりませんよね。変わったのはテクノロジー。テレビが薄くなったり、自動車がEVになったり、インターネットや携帯電話が出現したり。そもそもそんな技術を未来から持ってくるのがドラえもんです。今後も生き物としての人間が大きく変化することはありません。圧倒的に変わるのは道具の便利さと、文明のかたちです。
ドラえもんの作中に出てくる「タイムマシン」と「どこでもドア」「タケコプター」はいわゆる時空を支配する道具ですよね。「タイムマシン」があれば時間を、「どこでもドア」「タケコプター」があれば空間を支配できる。テレビやラジオは、別の場所にあるコンテンツを瞬間的に描き出せる、まさに時空を支配してコンテンツにアクセスできる道具ですね。
メディアの正体というか、私たちのメディア的な究極の欲望は、人間がどこまで時空を支配できるかということです。その意味で、ドラえもんは人類の究極のメディア的欲望をいきなり1巻から提示しています。
――メタバースという概念についてはどう認識されていますか?
FacebookがMetaと社名を改め、VR(仮想現実)の分野に本格進出を進めています。ではVRあるいはメタバースとは何か。その概念はいろいろな定義がありますが、そもそもあらゆる生き物は自分自身の「仮想現実」の世界に生きています。
目や耳や皮膚や舌や鼻など、生き物は外部からの情報を感覚器でとらえ、情報処理して脳内に再生します。逆にいえば、自分の感覚器でとらえられない世界は感知できない。ユクスキュルという学者が提唱した「環世界」が、それぞれの生き物にとっての現実です。同じ部屋にいても、僕とハエと猫では全く違う時間・空間把握をしています。感覚器が違いますから。同じ場所にいながら違う世界を生きていると言えます。
これは個々の人間についても当てはまります。それぞれが自分の感覚器で感知した世界を生きている。つまりもともと私たちは自分の「仮想現実=環世界」の住人なんですね。僕とあなたを比較してもちょっとずつ違うメタバースに生きているということです。
MetaやGoogleが考えているメタバース空間は、全員が同じ仮想空間であたかも身体も持っているように過ごしましょう、というもの。いわば我々が寝ている間に見る夢、あれはばらばらですが、おなじ空間でみんながそれぞれ夢を見ているような状況をテクノロジーで現実化しようとしているわけです。我々はもともと環世界=仮想現実に生きています。だから、ある意味で、メタバース空間はその延長線上にあるわけですね。
AR(拡張現実)も、ある意味ですでに実現しています。ARでは、世界のあらゆるリアルなものや場所にデータをタグ付けしていきます。個人レベルでは、それぞれすでに現実化しているんですよね。たとえば、僕の手元に昆虫図鑑がありますが、この昆虫図鑑の内容が頭に入っている人からすると、そのあたりにいる虫をみれば脳内で自動的に名前も習性もデータがたちあがる。でも、知識のないひとは、そもそも虫がいることにすら気づかない。
ARのサービスはだれもが、さまざまなリアルな物や場所についての情報がリアルタイムにアクセスできる状態を提供してくれる。そこが新しいわけですね。まさに、現実を拡張してくれるわけです。
あらゆる事象や場所に名前をつけ、知識を深めていく。人類がずっとやってきた知的行為です。ARは、その人類の積み重ねてきた知的資産を、リアルタイムに誰でもどこでも活用できる、共用できるようになる。そこが圧倒的に新しい。まさに知の民主化です。
ちなみにインターネットからはじまり、ARやVRにつながるテクノロジーが目指すのは、「時間と空間の支配」です。テクノロジーはより時空を支配する方向に進むと考えておけば間違いありません。
――時空支配とは、具体的にどのようなことが起きるのでしょうか?
まず、時間のほうです。テクノロジーは、私たちの時間の無駄をどんどんはぶいてきました。インターネットの普及とVRの発達は、移動時間を究極まで減らしてくれます。今回のコロナ禍をきっかけに、「通勤」という空間移動と時間消費のムダをなくした会社、いっぱいありましたよね。メタバースの初期形態のようなZoomのような場は、自宅から一歩も動かずに、国際会議をしたり、コンサートに参加したり、飲み会をしたり、とあらゆるコミュニケーションが可能であることを実証しました。私たちの脳をつないでできる仕事やエンタテインメントの多くは、メタバース空間でやったほうが効率がいいし、自由度も高い。まさに、時空の支配がここに実現するわけです。
一方で、忘れてはいけないのが私たちの身体です。おそらく身体そのものをバーチャルにすることは不可能でしょう。さらに、私たちが実際に住まう現実世界、生態系もリアルな存在であり続けます。身体と生態系、地学的な空間は保守的です。技術の進歩でなくなるものではありません。
となると、卑近な例でいうと、「どこに住むのか」という誰しもが当事者になる問いの前提条件が大きく変わります。これまで日本人の大半は「どこに住むのか」を決める時、第一条件として「通勤」をセットに考えていました。でも、仕事の多くがメタバース空間でできるようになると「通勤」は毎日の仕事ではなくなります。となると、「どこに住むのか」を選ぶ際の第一条件は「どう生きたいのか」ということに変わります。
つまり、メタバース、VRの発達によって、人々はむしろ自分が暮らしたいリアルな場所に対する興味と欲望を高めていくはずなのです。実際、軽井沢などのリゾート地や地方都市に移住して、そこから仕事をしている人たちがたくさんでてきています。私の友人にもいっぱいいます。このひとたちに共通するのは、「仕事はメタバースでけっこういける」「ライフは自分の好きなリアルな場所を選びたい」という考え方です。
となると、VRなどの発展は、通勤を第一に考えた結果うまれている過剰な過密都市、東京のいまのあり方を変える可能性があります。都会が好きな人は積極的に東京を選ぶ。ただし、それは通勤のためじゃなくて、自分のライフスタイルにあっているから。となると、通勤第一で都心志向だったひとのなかには、ライフ第一に考えたとき、東京に住む必要はない、むしろ海の近くがいい、京都がいい、沖縄がいい、自分の地元がいい、というケースがいっぱいでてくるはずです。
VRとARで私たちが、さらに時空を支配できるようになると、ある意味で「どこでもドア」や「タケコプター」(これはもうドローンですね)を手に入れてしまうと、仕事はVR空間、住まいは「好きなところ」というふうに二層化していくはずです。
世界一自然に恵まれている都市・東京の価値
――メディアビジネスや街づくりに関して、今後日本企業はどのような動きをしていくと思われますか?
日本企業が、アメリカのGAFAMのように、あるいは中国企業のように、インターネットやその延長線上にあるVRやARの空間の下部構造を支配するプラットフォームビジネスで大きく羽ばたくかどうか、未知数です。コロナ禍を経験し、これからVRやARが発展することが明確ないま、日本が磨くべきは、コロナ以前から進められていたインバウンド戦略の延長ではないか、と思います。円安はこのジャンルにおいては追い風です。
インバウンド市場において、日本にはいくつもの大きなアドバンテージがあります。
まず、観光という側面からみると、日本はとても価値が高い。たとえば東京って世界屈指の大都市は、世界でもっとも自然環境に恵まれた都市でもあります。夏は、日帰りでサンゴのある伊豆半島のような海でダイビングもできます。伊豆諸島も小笠原諸島も東京都ですね。冬になれば、やはり日帰りでスキー場にアクセスできます。世界中のあらゆる大都市で、こんなに自然にアクセスが簡単にできる大都市、実はありません。東京、といえば、大都市ならではのアミューズメントばかりが目につきますが、実は「自然」が売りになりえる場所です。
これは東京にかぎりまぜん。日本は、世界屈指の自然豊かな国です。理由は明確です。南北に長い地形なので、亜寒帯から亜熱帯までが含まれ、火山列島なので地形が複雑で景色も豊か。農作物も魚類も多様で、食文化も発達している。
コロナ禍を経て、ふたたび世界の観光需要が増す中、日本のこうした観光資源は巨大な経済価値になります。
しかも、日本はやはり相対的にみれば世界でも治安がいい国です。さらに、今後はリアルタイムの翻訳や通訳アプリが発達していきますから、英語はもちろん各国語を普通の人が活用できるようになります。
――未来では、自動運転車やスマートシティの開発も進んでいるかと思います。日本の街の風景は、テクノロジーによってどう変わっていくと思われますか?
日本の、とりわけ首都圏や京阪神の都市の特徴、それは、世界でも鉄道網が非常に発達していることです。このため、日本ではまちづくりを鉄道主体に考えることが基本でした。都市部はもちろん地方でも、です。けれども、1990年代以降、日本の自動車保有台数は急増し、東京都心を除く日本の大半の地域では、鉄道から自動車へと交通手段の主役が交代しています。2000年代以降、現在に至るまで、小売業のランキングの上位は、郊外型で自動車でアクセスするショッピングモールやドラッグストア、量販店が占めています。
一方、地方では鉄道駅の周辺にある商店街の高齢化、シャッター化が問題となっています。そこで、日本でもアメリカのように自動車でアクセスできる郊外型のエリアに、人々が歩いて街を楽しめる新しいダウンタウンのニーズが高まるはずです。アメリカでは、自動車が必要な郊外のエリアに八百屋やおいしいカフェ、アンティークショップがあったりします。いわばモール形式のまま、その隣に個人店ができています。
日本では、道の駅がある意味でその先行事例かもしれません。地元の農協・漁協が道の駅とちゃんと提携して、地元の野菜や魚を売る。そういった道の駅的な場所をもっと構造化し、新しいロードサイド型の街を形成していく必要があります。
自動運転・半自動運転車の技術が発展すれば、高齢化した地方においても、人々が自動車を活用した生活を続けることが可能になるはずです。
街の見た目には変化がないと思います。テクノロジーは発展するほど、息をするように当たり前の存在になり、いままでの生活の中に、ハードではなく、ソフトウェアとして実装されていきますから。銀河鉄道999や鉄腕アトムに出てくる宇宙のような都市にはたぶんなりません。ドラえもんの世界がずっと変わらないのと同じように、一見いまと変わらぬ街に、最新のソフトが実装されていくのではないでしょうか?
「土着性」の高いコンテンツづくりが重要
――街の見た目には変化がない一方、今後、バーチャルの世界はどの程度まで拡大するのでしょうか? 利用者の特徴など、お考えを伺いたいです。
若者か老人かは関係なくなるでしょうね。今も電車に乗れば、みんな年齢問わずスマホを見ています。そういう意味で、我々はとっくにメタバースの中に入ってしまっているのです。人間は適切なメタバースが大好きなので、技術の発展に伴って老若男女問わずどんどんメタバースの世界へ行くと思います。
ポイントは、コミュニケーションするメタバースです。例えば、人間は150人以上を認知できないとされています。この認知機能の限界は永遠に変わりません。だから、ベースになるのは150人の村ということになります。
暮らしと仕事の場所に加え、サードプレイスを持っていたほうがいいと言いますが、人間はすでにいくつかの村を行き来しています。しかし、このようなリアル世界のメタバースは、身体の移動を伴いますよね。一方で、SNSを含めたインターネット上のメタバースは、身体を伴わずに、脳と心を預けられるものです。
こうなると、ある意味で人格が分裂された世界になっていくとは思いますね。人間は元々いくつかのキャラクターを自然に作っているものです。それがメタバースによって可視化されるだけで、コミュニケーションのサイズ感は変わらないでしょう。
――メタバースの普及によって、人々のコミュニケーションツールはどう変化していくのでしょうか?
例えば、何かのコミュニティが作られた場合、そのテーマや趣味嗜好に準じた広告がプッシュされるようになるでしょう。
ここ15年のインターネット広告は、ターゲティング機能によって「いつ、誰に見せるか」という方向へ、つまり「広告」から「狭告」へと変貌していきました。
ただし、これから広告の価値は、コンテンツのクオリティがより問われるようになる、と思います。つまり、「どんなコンテンツを見せると気持ちよくなってもらえるか」という広告の持っているプリミティブな力が再び重要になる。そう思います。
そこに流れてくる広告的なものが気持ちいいものであって、面白いものであり、むしろ積極的に指を止めて見たくなるようなものでない限りダメだという形になるということです。そうすると、やはりクリエイターの仕事が重要になると思いますね。
――最後に、2040年のメディアやコミュニケーションはどのようになっていると思われますか?
インターネットが出てきてから、かつてはメディアごとに別々だったハードウェア・プラットフォーム・コンテンツが同じ舞台に乗るようになりました。テレビもラジオも雑誌も新聞も書籍も映画も電話も手紙も、すべてネット上で流通し、すべてスマホで再生できる。すでに4大マスメディアという切り分けは事実上消えつつあります。新聞的なテキストの速報、雑誌的な特集記事、写真集のような画像、テレビのような動画ニュースをどのウェブメディアも当たり前のように流していますよね。
となると、プラットフォーム争いから、次に起きつつあるのは「優秀なコンテンツ」を創造できるかどうか、です。優秀なコンテンツを創造できるひとや組織は、どのプラットフォームも喉から手が出るほど欲しい。実際にアニメーションや映画の世界では、国境を越えた才能の争奪戦が起きています。
そこで重要なのは、どれだけ継続的にプロダクション機能を担う人を育て、コンテンツを作っていく仕組みができるかという点です。マンガのように、新人の発掘から大物に育て上げるまでを担う人材育成の仕組みが、もっといろいろなコンテンツの世界に広まって欲しいですね。
世界中が繋がってしまうからこそ、付加価値や差別化が必要になります。そこで、注目したいのが「土着性」です。VRが発達するほど、自分の身を置く場所が重要になるのと同様で、人間と文明が持つ土着性のようなものは、ネットで払拭されたりしません。むしろ個々の土着性を活かしたコンテンツづくり、重要だと思います。観光ビジネスとその点は通底しますね。日本の土着性を生かして、オリジナリティある面白いコンテンツをどうやって生み出していくのかがポイントです。
韓国ドラマがすさまじいクオリティですが、Netflixのような世界市場で活躍している一方、いずれのドラマも韓国でないと生まれない、土着性を持った物語です。物語がものすごくハードなのに、ちゃんとエンターテインメントして面白くて、子供も見られてしまう。あれは、やはり韓国の中だから生まれてくるコンテンツだと思います。
最後に。あらゆるメディアビジネスは「観光」的側面を持っています。つまり、その土地、その人じゃなければできないなにかを、お客さんに楽しんでもらう。自分の見慣れた日常の中から、「観光」になる要素、切り口、見立てを再発見する。日常の中にワンダーが隠れている。そんな「ドラえもん」的な発想こそが、エキゾチックなものをひたすら見せる宇宙SFより、実はクリエイティブだったりします。
そして、そんな日常のワンダーは、日本のどこででも発見できるはずです。
2021年12月22日インタビュー実施
聞き手:メディア環境研究所 冨永直基
編集協力:有限会社ノオト
※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。