「モノ」にも人権を見出す必要がある 建築家・豊田啓介氏が思い描くデジタル時代の未来都市と建築
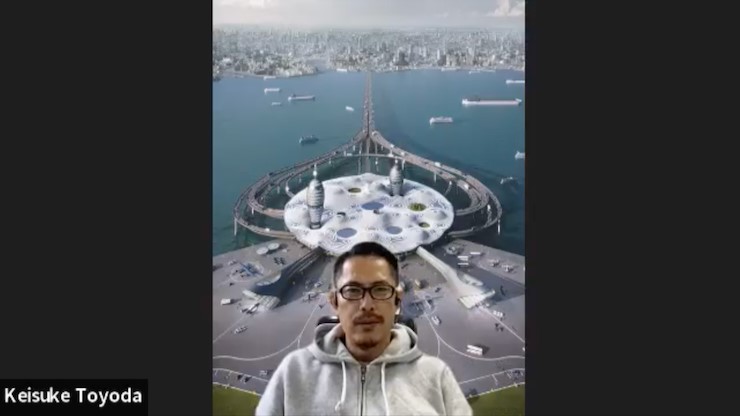
博報堂DYメディアパートナーズのメディア環境研究所は、テクノロジーの発展が生活者や社会経済に及ぼす影響を洞察することを通して、メディア環境の未来の姿を研究しています。少子化・超高齢化社会が到来する中、本プロジェクトは現在各地で開発が進められているテクノロジーの盛衰が明らかになるであろう2040年を念頭に置き、各分野の有識者が考え、実現を目指す未来の姿についてインタビューを重ねてきました。
デジタルと建築の融合の先には、どんな未来が待っているのか。建築デザインだけでなく、都市のデジタル化を通じたスマートシティの実現、リアルな都市や建築物と3Dで記述されたデジタル空間を媒介する領域を意味する「コモングラウンド」の社会実装を目指す建築家の豊田啓介氏に、都市や住宅の変貌、建築とデジタルとの関係性について話を伺いました。

「人」と「モノ」をシームレスに捉える
――建築家である豊田さんが取り組んでいるテーマや現在の関心領域を教えていただけますか?
住宅やインテリアなどを設計する中で、デジタルによってそれらの本質がどう変わっていくかに興味をもちました。それで、コンピュテーショナルデザインやパラメトリックデザインの本場であるコロンビア大学に留学したんです。
その後、ニューヨークで働く中で、設計と施工をデジタル技術で融合する動きを目の当たりにし、それをアジアでやるとどうなるのかへ興味が湧き、日本に帰ってきました。
――帰国後は、どのような活動を行っているのでしょうか?
現在は日本とアジアで、デジタル技術によって設計と施工の再価値化ができるのではないかと考え、活動しています。
通常だと、建築は建物を顧客へ引き渡したら終わりです。しかし、建物はむしろ引き渡したあとに使われて価値化するもの。だから、デジタルデータを建物に重ねることで生まれる可能性は、今の「建築」という業態の外側にあるはずなんです。
そう考えているうちに、設計だけでなく、他の業態を横断した未来社会を実現するためのコンサルティング業務なども手掛けるようになり、スマートシティをテーマに掲げるコンサルティング会社・gluonを立ち上げました。
その流れで、今は万博誘致にも関わっています。正直、以前は万博はオワコンだと思っていたんです。しかし、スマートシティとはモノが新しくなるのではなく、その背後にある情報の移動による価値の再編成にこそ本来の価値があると考えるとすると、今の万博はそれを仮設で作れる点でものすごく価値があります。なので、現在は万博を1つの旗印に、複数の企業を巻き込むプロジェクト「コモングラウンド・リビングラボ」をやっています。
――新しいインフラ構築には長い時間が必要です。20年後の都市にとって、何が重要になると思われますか?
何よりも、人間を唯一の主体と考えないことです。今のように「人」と「人ではないモノ」という二項対立的な捉え方ではなく、いかにそれらをシームレスに捉えるかという感覚が重要になってくるでしょう。これは、「いかに人以外のモノがもつ人権を見るか」に集約されると思います。
例えば、今のバリアフリーの文脈では、身体が不自由な人が行為者であり受益者です。しかし、ロボットにとって動きやすい街やARアバターが認識しやすい部屋のデザインなどはバリアフリーと認識されていません。
でも実際には、ARアバターが動きやすい空間にいることで都市と地方の格差を感じず社会に貢献できる人や、ロボットに乗ることで初めて行動ができる人もいます。将来、自分のお母さんがロボットに乗るようになるかもしれません。
机や建物、ロボット、アバターなど人ではないモノの権利や、それらが動きやすい社会を考えるという視点は、間接的に人につながっていく。だからこそ、この感覚で人間以外のいろいろなモノを見ることが、すごく大事になってきます。
――現在、ロボットやモビリティと人間が交流できるテクノロジーはどのくらい実現に近づいているのでしょうか?
要素技術は、すでに結構できあがっていると思います。ただ、今はその技術をエッジ側(ロボットやモビリティ本体側)に100%積んで処理する形なんです。
例として、自律走行のロボットを考えてみましょう。今は1台のロボット中にLiDAR(光を用いたリモートセンシング技術の一つ)やデプスセンサー、光学カメラなどの技術がすべて入っています。
ナビゲーションやデリバリーなど10社分の複雑な仕組みが、ロボット1台にすべて詰め込まれ、さらにそんなロボットが1つのオフィスビルに50台も動き回るとしたら、これは大変なコストで全体調整もできません。だから、実用化は無理なのです。
しかし、1社のロボット1台にすべての技術を積むのではなく、管理をする環境側にLiDARを設置し他の会社のロボットも含めて位置情報などをシェアすれば、コストを劇的に落とすことができます。
これは、現在の要素技術とはネットワークの仕方や使い方が全く違うため、新たな技術は当然必要になるでしょう。けれど、今ある技術の組み合わせを変えれば、5年後くらいまでには作れると思いますね。
――そうなると、2040年には自動運転車は一般的になっているのでしょうか?
なっていないとおかしいです。ただ、今も5Gが入るところと入らないところがあるように、全国でフラットには進まないでしょう。まずは東京23区内や環七の内側だけなど、地域ごとに実装のスピード感に差はつきつつも、環境整備が進んでいくと思います。
人が乗るための自動車以外にも、歩道を走るデリバリーロボットや空港や駅の中で動くロボットなど、場面に応じて仕様は異なります。それぞれの専用システムやシステム同士が連携できる環境を作るためのインセンティブ制度もできてくると思いますね。
バーチャル×リアル=無限の可能性 都市を選択させられる今の人々
――都市の発展や運営において、リアルとバーチャルのコミュニティはどちらがより重要になっていくのでしょうか?
そもそも今の時点では、バーチャル側の要素が完全に足りていません。つまり現時点では、人間が社会活動をする場所として、リアルとバーチャルの間には接続しようがないくらい差があるのです。
しかし、バーチャルに抽出できるのは形や重さ、硬さなど、リアル世界に仕込まれている無限の情報の中にある一部のチャンネルだけ。接続の違和感を減らすためには、まずはバーチャル側のチャンネル数を増やし、高解像度にしなければなりません。そのために、新しいセンサーや通信技術、もしくはコモングラウンドのようなシステムなど、バーチャル側への投資が必要なのです。
今の社会は、モノありきの社会であり、モノがなければ価値領域も存在しません。でも、リアルの情報を抽出してバーチャル世界で再編集できたら、全てが価値につながり、それだけ社会的にはとんでもない新大陸になるはずです。チャンネル数が有限のバーチャル世界と無限のリアル世界をどれだけ混ぜ合わせて、どれだけ編集可能にできるかは重要なポイントだと思いますね。
そのためには、いつでもどこでも情報が取り続けられないといけません。しかし現在、リアル世界に存在する情報にはデジタル記述ができないという問題点があります。
実空間とサイバー空間の間でデータ・情報が行き来する領域「インタースペース」は、この2つの空間が常に重なっている状態を担保するという考え方です。あらゆる挙動が常にデジタル記述されることで、可読性が高く粒度が揃ったAIが読み取れる情報として常に流通させられるようになります。インタースペースによってビックデータを流通させるためには、やはりコモングラウンドが必要になるでしょう。
――2040年を生きる人たちは、都市、あるいは田舎に住むのかをどのように決めていくと思いますか?
生活レイヤーの中で何を重視するか。その判断や選択は、より明確で個別的になるはずです。今は「自分の存在=身体」で、その場所を体験するには身体を置くことが必要です。なので、オフィスの立地や子どもの教育機会などを考えると、9割の人が都市を選んでしまいます。
でも、彼らもあらゆる面で都市を選びたいわけではないと思います。できるならば、生活の3割くらいは田舎に住んだり、地元の伝統芸能も継承したり、自然の中で子どもを育てたりしたい、と考えている人もいます。でも、残り7割の生活を考えると、各選挙区でたった一人しか当選しない小選挙区制選挙のように、都市という一択を選ばざるを得ないのです。
しかし、「自分の存在=身体」とならず、情報が離散化できるようになれば、田舎に住みながら東京の仕事をする、地元で子どもに神楽を継承させながら都会の学校に通わせることも可能になるでしょう。
身体の拠点も固定せず、1カ月の間に2週間は都市で、10日間は田舎で、5日間はリゾート地で過ごすなど。そういう離散化と流動化は必然になると思いますね。それができれば、都市を強制的に選択させられている人たちも分散するでしょう。
――都市開発においてコミュニティの存在は重要です。街ごとにコミュニティのあり方は変わっていくのでしょうか。それともバーチャル世界でのやりとりの重要性が上がったら、あまり変化しなくなっていくのでしょうか?
そもそも、全ての都市が同じように発達するのは不自然でありえないことです。リアルなコミュニティのネットワークが強い街もあれば、そうでない街もある。そういう棲み分けがまちづくりの選択肢になってくると思います。
豊かな自然がある、スポーツに適している、寺院や歴史の蓄積がある、農業に発達しているなど、田舎にもいろいろな方向性がありますよね。それを戦略的に整備することによって、0か100かでいえば0になってしまう場所にも人が流れこみ、地方経済が回るようになっていくのではないでしょうか。
また、「公共」も問い直されると思います。現在は、自治体によって土地の境界が管理されていますが、実態と合わなくなってきていますよね。例えば、目黒区に住んでいるからといって、目黒区だけで生活するわけではないですし、世田谷区に一歩入った瞬間に受けられるサービスの前提がすべて変わるというのはおかしな話です。
今後、民間企業が土地に紐付かない公共サービスをやる割合が増え、反対に自治体が民間サービス的なことをやらざるをえなくなるケースが増えていくでしょう。民間企業の公共性と公共団体の民間性の境界線は曖昧になって、シャッフルされていくと思います。
変化するのはモノの形ではなく「情報の編集性」
――拠点の離散化・流動化をふまえ、今後、住宅のあり方はどのように変わっていくのでしょうか?
これからのスマートシティの特性の一つは、モノ領域を変化させないことです。例えば、配車アプリに革命が起きたとしても、タクシーの車体そのものを変えることを要求しません。つまり、タクシーは物理的にはタクシーのままなんです。そのようにモノ自体の改変や移動をさせずに、情報の編集だけでスマートシティ化していくでしょう。
モノは大きくなるほど、物理的な面が圧倒的に強くなります。特に建築物ほど大きいと、モノとして成り立つことが絶対的に勝ってしまうので、どうしても物理的な形は変わりづらくなっていく。
移動する都市が意味するのも、物理的に移動させるのではなく、あくまでも情報の編集でモノや人の移動、その機能の改変を代替してしまうこと。だから2040年になっても、モノや都市の形は意外なほど変わっていないと思います。
一方で、家族や居住のあり方は自然に変わっていくでしょう。1カ所に居住しなくてもいい、複数の学校に同時に所属してもいい、家族も別に1つでなくてもいい……。今後、「社会常識だと思っていたけれど、そうでなくても良かったんだ」という気付きがたくさん出てくるはずです。違和感を覚える人も当然いるでしょうが、シェア家族やレンタルパパがいるほうが正しいと感じる人が出てくるのは充分ありえます。そういった感覚は、2030年にはもう広まっている気がしますね。
――世界では、リアルとバーチャルが融合するという文脈で「メタバース」が盛り上がっています。日本におけるメタバースの認識は少し違うのではないかと感じていますが、いかがでしょうか?
定義があるわけではないのですが、そもそもメタバース=VRという認識になっていることがミスリードですよね。メタバースはもともと高時空間のインタラクションを含んだ言葉。そのため、本来の意味でのメタバースは、僕の言っているコモングラウンドに近いものだとは思います。コモングラウンドがあることで初めて、モノと場所とエージェントの相関性が、どちらから見ても担保される。
今言われているメタバースって、「自分」という主体が特殊解で、自分から見た周りの世界でしかないじゃないですか。でも、本来のメタバースは他人から見た自分や、場所から見た自分や他人が全部等価になっているものなのではないでしょうか。メタバースのほんの一領域でしかないところが騒がれているだけのような気がします。
日本には「八百万の神」という感覚を持っている人がたくさんいるので、本来のメタバースに近づく素養はあると思います。しかし、せっかくこのような土壌があるにもかかわらず、技術の実装やマーケティング、産業へのインプリメンテーションなどをアメリカにとられてしまっているのはすごくもったいない。
他国がスマートシティ実装に失敗した原因はデータ収集・活用を念頭に起きすぎて、個人のプライバシーを阻害しすぎたことにあります。その点、日本にはモノの背景にいる人間を想定してスマートシティの実装ができる大きな可能性が残されているのではないでしょうか。
――最後に、2040年のメディアやコミュニケーションはどうなっていると思われますか?
「インタースペース」という考え方は、空間自体がメディアであり、UIであり、UXであるということを意味します。
ほとんどの場合、サイバーフィジカル連携において、IoTデバイスは物理空間と情報空間をつないでいるだけ。現在もインターフェースと呼ばれる面を窓として情報をやりとりしていますが、明らかに情報が足りていません。
2040年には、空間そのものが全部インターフェースになり、その活動が軒並み情報と重なっていて、その情報が常に可読な形で取れるようになっている。それ自体がメディアとなっているはずなので、インターフェースであることを意識する必要もなくなっているでしょう。ビジュアルベース、人間視点ベースにこだわらないものに拡張しているんだろうな、と想像します。
2021年12月6日インタビュー実施
聞き手:メディア環境研究所 小林舞花
編集協力:有限会社ノオト
※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。



