メディア環境を語る メ環研×テレビ東京×東急(前編)スクリーンの外にある生活を豊かにするためには?
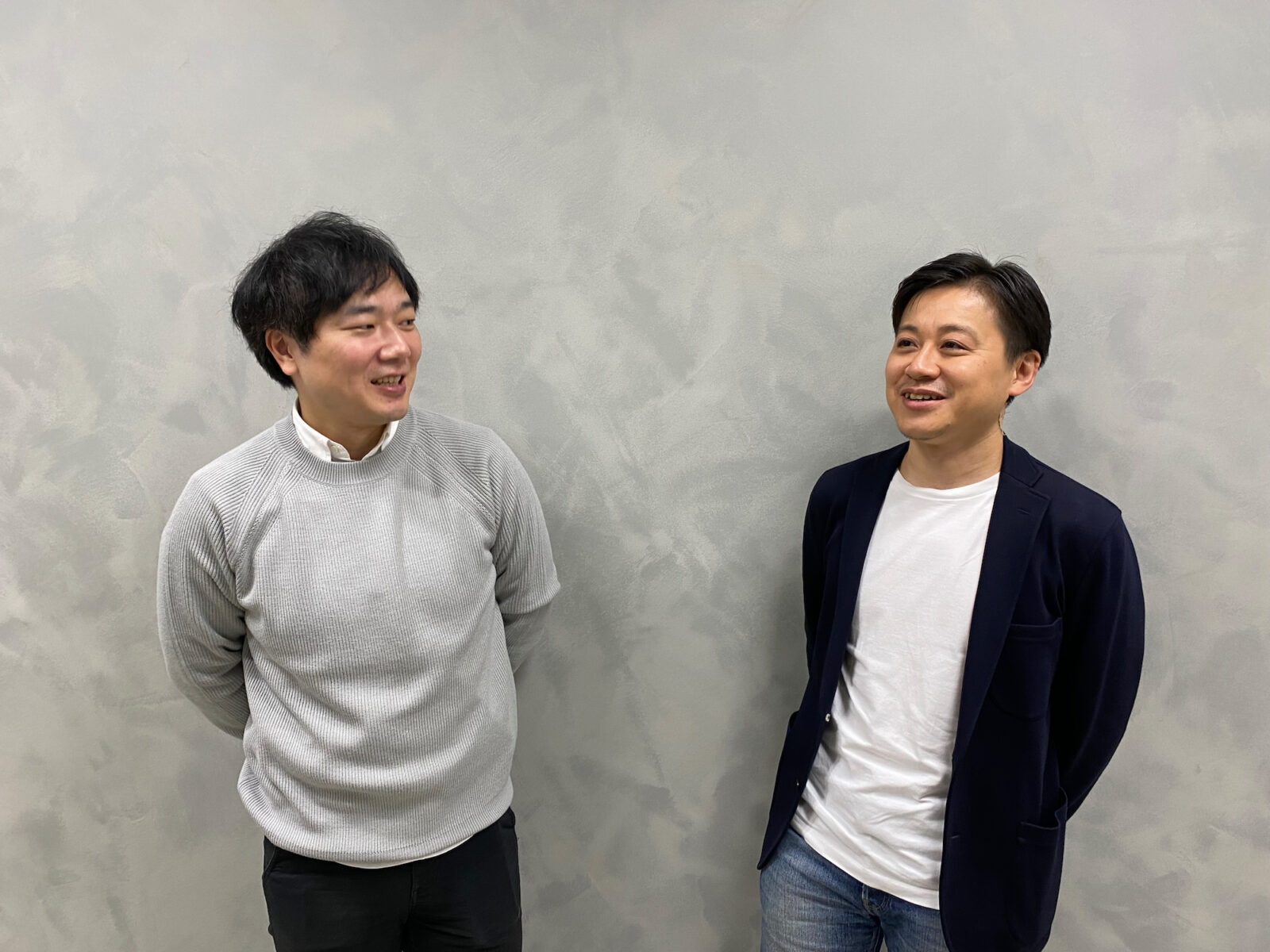
メディア環境研究所では、デジタル化によって大きく変化したメディア環境をスクリーンという視点から捉えるため、従来から実施中の「メディア定点調査」に加え、2023年9月、新たに「スクリーン利用実態調査」を立ち上げました。その調査結果をベースに、有識者と今後のメディア環境について考える連載を行っています。
第2回は、株式会社テレビ東京 アニメ局アニメ事業部の合田知弘さんと、東急株式会社 デジタルプラットフォームURBAN HACKS シニアシステムプロデューサーの長谷川晋介さんに話を聞きました。
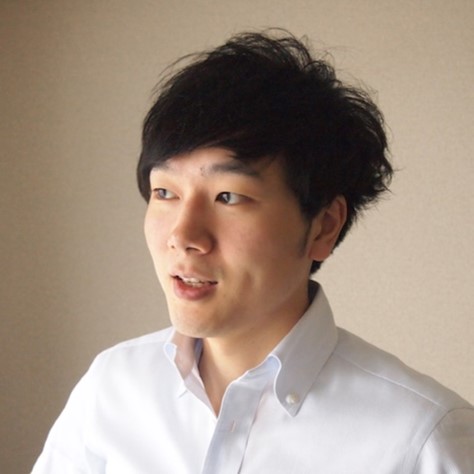

リアルタイムの熱狂とオンデマンドのハイブリッドで、コンテンツを届ける
――合田さんと長谷川さんはテレビ東京でのご同僚でしたが、現在、長谷川さんはまちづくりという視点で生活者の行動や変化を捉えていらっしゃいます。放送局の視点との掛け合わせによる化学反応から、どのようなメディア環境が見えてくるのか楽しみです。はじめに、お2人の経歴と現在のお仕事内容について教えてください。
合田:2006年にテレビ東京に入社後、人事部での新卒採用担当を経て、ビデオグラム化や海外番販、ドラマの製作委員会幹事など番組コンテンツの周辺事業を5年間ほど経験した後、テレビ東京コミュニケーションズというデジタル事業の会社へ出向しました。VODサービスの立ち上げや、スマホを使って視聴者のエンゲージメントを高める企画づくりに携わり、そこで長谷川さんと一緒に仕事をしていました。
その後は本社の編成に戻り、ウェブやアプリなど配信サービスやTVerを含むデジタル戦略の担当、ドラマのプロデュース等を経て、2022年秋にアニメ事業部に異動しました。現在はアニメの製作委員会への出資など、テレビ東京での放送や配信でお届けする作品の立案や窓口運用などのビジネス周りを担当しています。
長谷川:テレビ東京在籍時は「テレ東BIZ」という報道番組の配信サービスに携わっていました。私は元々エンジニアで、最初はアプリ開発やシステム基盤を作っていましたが、広告会社さんとのプロモーションや事業分析なども経験しました。
その後、2022年に東急株式会社に移りました。東急は沿線のまちづくりをしているのでリアルの接点は多いのですが、デジタルはそこまで強くありません。そこで、社内でアプリやウェブを作るため、ゼロから組織を立ち上げました。それがURBAN HACKSです。
東急株式会社の連結子会社であるグループ会社は約130社あり、デジタル面で連携するといっても簡単ではありません。とはいえ「デジタル面でサポートしてほしい」という依頼は多いので、各社の情報システム部などと一緒に取り組んでいます。
――130社もあると「いま何に困っているのか」「それをデジタルでどう解決できるか」を見つけるだけでも大変ですよね。
長谷川:おっしゃる通りです。「デジタルを使いたい」と相談されたときは必ず「デジタルはあくまで手段ですよ」という話をします。単にアプリを作るという話ではなく、どういう課題があって、どんなことをしたいのかが重要です。
2023年には東急歌舞伎町タワーを開業しました。昨秋、そのタワー前広場で私が紹介した会社さんとK-POPのダンスイベントを共催したところ、数千人が集まり大成功でした。普段歌舞伎町に来ることがないような小さな子どもたちも集まって盛り上がりました。私自身は紹介をしただけでイベント企画に携わったわけではありませんが、どんな形でも何らかの成果に繋がるような手助けができれば、関係会社とのコミュニケーションも増えて関係性もできてくる。「デジタルを使って何かやろう」という話にもつながりやすくなりますよね。コミュニケーションを大切にしながら関係性をつくって、新しいものを生み出していこうとしています。
――メディア環境研究所では、昨年初めて「スクリーン利用実態調査」を実施しました。この結果を見て、合田さんはどう思われましたか?
合田:コロナ禍で動画配信サービスの利用者が伸び、コネクテッドTVでの動画視聴のバリエーションも増えました。また、すきま時間にスマホで動画コンテンツを見る習慣も浸透しています。この流れは、コロナ前の推移と比べると加速度が増しましたが、想定を超えるほどではなかったと感じます。

合田:とくに若い人たちは、「1日の中でスクリーンを見ていない時間ってある?」くらいの感覚ですよね。さらに言うと、現実にはもっとスクリーン接触時間が長いかもしれません。例えばスマホでSNSやゲームをしながら動画配信サービスなどがピクチャインピクチャやバックグラウンド再生で立ち上がっているといった状況も生まれていると思います。そこに倍速再生なども相まって、”タイパ感覚” を意識しながら重層的に、複数のスクリーンやメディアに同時に接触している。それを踏まえてスクリーンへの総合的な接触面積を考えると、実態としてはこの結果よりも大きいのではないでしょうか。
――なるほど。スクリーンの中はすでに飽和状態ともいえますが、生活者に対してどのようにコンテンツを届けていこうと考えていますか?
合田:いつでもどこでもオンデマンド視聴できるウィンドウの整備は大前提としても、リアルタイムの”ライブエンタメ感”も併せて際立たせていきたいです。推しのアーティストが出る番組をリアタイしたい欲求はあるし、好きなアニメをファン同士、SNS上でシンクロしながら視聴したい感覚もある。その瞬間でしか体験できないものや、盛り上がるための”余白”を提供する重要性はなくならないでしょう。
デバイスや提供メディアの変化で緩急をつけながら、リアルタイムの熱狂とオンデマンドの利便性のハイブリッドをいかに研ぎ澄ましてお届けしていくか、の勝負ですね。

――アーカイブの見せ方、届け方についてはどう考えていますか?
合田:過去の作品を、あえてこの瞬間にお届けすることで生まれる価値もあります。例えばTVerで新作関連のドラマ・アニメ過去作を一挙配信するように「今、これを見ておいた方がいいよ」というキュレーション的な届け方も、スクリーン飽和状態においては今後いっそう重要になっていくと思います。
――コロナ禍以降、TVerの存在はとても大きくなりました。アニメについてはどうなのでしょうか?
合田:個人的な感覚ですが、アニメ業界の中では、TVerとの向き合い方は作品によってもかなり異なるかと思います。アニメは、テレビ局も主要なプレーヤーの1つではあるものの、(放送直後にTVerに多くの番組が並ぶ)局制作のバラエティやドラマなどと違い放送局単独で権利をハンドリングできる作品ばかりではありません。
一方で、アニメのファンの方は有料動画配信サービスの加入割合も高いと言われます。一般的な製作委員会の考え方としては「多くの方に作品をお届けする」ことと「ビジネスの収益を上げる」ことの二輪を回していくための最善の選択を考えています。
――最善の選択とは、具体的には?
合田:一般的には製作費を回収するためにはSVOD(Subscription Video On Demand:定額制の動画配信サービス)でまずは収益を積み上げていく、というのが実情かと思います。特にアニメ作品は1つのプラットフォームによる独占配信や先行配信、複数社による共同独占配信、非独占配信などさまざまな配信の形があります。またアニメについては全世界に届けるべく日本国外のエリアも含めて配信許諾するケースもあります。
もちろん、作品をたくさんの方にお届けするには、プラットフォームを制限しない(非独占)で進めるという手もあります。しかし、製作委員会の収益を考えると、バランスを取って進めなければなりません。1社に独占させれば収益は上がりますが、逆に視聴者へ届きづらくなる可能性も併せ持っています。
最近では複数のプラットフォームが段階的に先行して配信した後、プラットフォームを解放して非独占で作品を広げていく形が多いかと思います。もちろん放送直後からTVer配信をしている作品も多くありますが、そういった非独占配信のプラットフォームの中にTVerも入ってくるのも一例かと思います。
場を提供して、その街に住む意味や理由を作っていく
――コロナ禍によって、メディアと生活者をとりまく環境は大きく変わりました。長谷川さんは、生活者の変化についてどのように捉えていますか?
長谷川:テレワークで出勤しなくなった点は大きいですね。東急でいえば電車の利用者が減りました。今はやや戻ってきていますが、コロナ禍前の水準に戻すのは難しい。生活様式が変化した中でどう取り返していくか、を考えているところです。
具体策として実証実験を始めたのが、デジタル乗車券サービスであるQ SKIPを通して販売する、QRコードやクレカタッチ機能を活用した企画乗車券です。従来の企画乗車券は主に紙で、駅に行かないと買えないので手間がかかるし紛失の危険もある。でも、デジタルなら事前に購入でき、乗るときもスマホだけで済みます。 コンテンツの面では、東急線沿線の情報をもっとデジタル化して生活者に届けたい。特に「コンテンツを使って、生活者が移動する理由を生み出していこう」という話はよく挙がりますね。

――コロナ禍でテレワークになり、「オフィスまで電車1本で行ける」など通勤のメリットが薄くなった半面、「なぜ今、ここに住んでいるのか?」の意味を改めて考えた人も多いような気がします。街に住む魅力について、どのように考えていますか?
長谷川:たしかに、移動しなくなったことで自分の街にいる機会が増えました。これまでは会社帰りに消費していたけど、住む街では何をどう消費していいかわからない、という状況がありますよね。
その街の情報を一番知っているのは住んでいる人たちのはずです。だったら、街に住んでいる人達がほしいものをあげていって、それを我々が受け取り、必要なものがあれば住む人たちを含めた“みんな”で作っていく発想が求められるのではないでしょうか。
――具体的に動いている企画はありますか?
長谷川:生活者起点でのまちづくりを推進するプロジェクトを進めています。最初に作ったのが「nexusチャレンジパーク早野」。あざみ野駅からバスで約10分の場所にある土地に公園を整備し、地域の皆さんに提供する取り組みです。
例えば、「ネット販売だと人とのつながりを感じにくいから、リアルの場で売りたい」という要望は結構あります。でも、1人では難しいし、場所を探すのも大変。そこで、我々が場を提供しているわけです。

長谷川:「フリーマーケットをやりたい」「イベントを開催したい」という人は、必ず街にいるはずです。そこを我々が支援して街の魅力が上がっていけば、その街に住む意味や理由を作れるかもしれません。
――「毎日通勤して、家に帰ったら寝るだけ」みたいな生活だと、住んでいる街の魅力は分からないですよね。
長谷川:東京って1駅違うだけでも違う街みたいなところがあると思う。例えば、二子玉川と上野毛。たった1駅違いですが、街の雰囲気は全然違います。上野毛に美術館があることなどは、あまり知られていません。実は近くの街にも魅力がある。それをうまく発見できる仕組みをデジタルで作れると面白いかな、と考えています。
スクリーンの外にセレンディピティをつくり、情報接触をより豊かに
――1日中スクリーンを見ている生活だからこそ、“スクリーンの外”についても話しあいたいと感じました。アウトドアメディアのポテンシャルについて、どう考えていますか?
合田:スクリーンの中だけで考えると、新しいものに出会う機会や新鮮さを生み出すのは難しくなっていきますよね。SNSのアルゴリズムによる”出会い”も重要ですが、スクリーンの外での移動時間に着目したり、街の中にIPやコンテンツを落とし込んでいく価値を見直していくのも面白いと最近感じています。人気アニメで、渋谷や新宿など都市部の駅中心にメディアジャックを実施することも増えてきました。生活の中で自然に目に触れてもらう機会をどう醸成するかが重要です。
たとえば僕は外を歩くときに位置情報ゲームを起動することが多いのですが、ただスマホでコンテンツを消費するだけなら続かないかもしれません。健康目的など生活習慣の中に落とし込むことでもっとそのIPやコンテンツを好きになるきっかけがあると感じます。
長谷川:一日中ずっとスマホを見ているかというと、そうでもないでしょう。デジタルだけではなく、リアルも含めてどうカスタマイズしていくか。押しつけるのではなく、「気づいたらいるな」くらいにうまく溶け込めると親近感がわくのではないでしょうか。
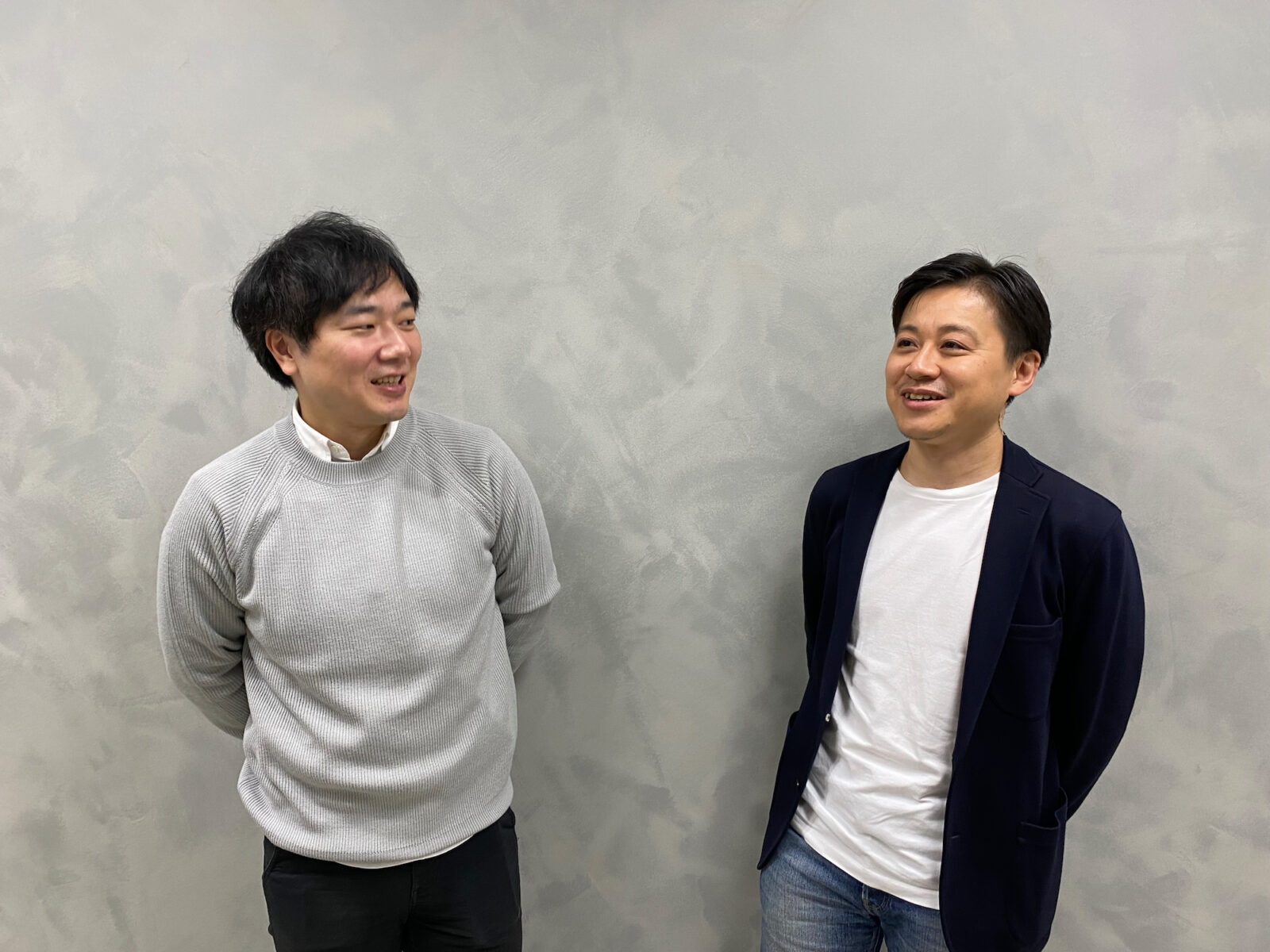
――スクリーンを見る時間が増えていくと、消費感はあっても体験感が減って疲れてしまいます。ただスクリーンを情報で埋めていくだけではなく、スクリーンの外とどうつなげていくか考えないといけませんね。
合田:以前、東急歌舞伎町タワーのTHEATER MILANO-Zaで舞台を観たのですが、舞台と同じIPのコラボレーション企画も同時に展開されていて盛り上がりを感じました。そういう先鋭的な取り組みの一方で、ローカルメディアなどエンタメ化されていない情報との接触も大事です。その緩急とバランス、ですよね。
長谷川:当社としては、リアルな体験を中心にしつつ、コンテンツホルダーの方々と連携を密にしていく必要があると考えています。
合田:放送局も、東急さんの手掛ける都市開発や生活サービスリテールといった生活に密着した事業との協業がより重要になっていくと思っています。スクリーンの外側に染み出していくことで、情報に触れる機会がより豊かになっていくのかな、と。
生活者の目線でいえば、スクリーンの中と外のメディア接触が行き来して、心地よいバランスを見つけていくスタイルになっていくのではないでしょうか。
2023年11月30日インタビュー実施
聞き手:メディア環境研究所 新美妙子
編集協力:村中貴士+有限会社ノオト
※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。

