AI時代は「人間力」やコンテンツの「深さ」が価値になる 起業家/エンジェル投資家 けんすう氏が読み解くメディアの未来
博報堂メディア環境研究所では、AIが社会や産業、メディアにもたらす影響について研究・洞察するプロジェクト「AI×メディアの未来」を立ち上げました。その一環として、さまざまな分野で活躍している有識者にインタビューを重ねています。
今回お話を伺ったのは、アル株式会社代表取締役の古川健介(けんすう)さん。けんすうさんはインターネットコミュニティの創成期から活躍し、「したらば」「nanapi」などのサービスを世に送り出してきました。現在はNFTやAIなど新しい技術を活用し、自社サービスの開発・運営や、企業向けの支援事業を行っています。
けんすうさんは、AIやWeb3、NFTなど新しい技術がもたらす社会構造の変化を、どのように捉えているのでしょうか。「もはやAIなしでは仕事ができない」と語るけんすうさんの視点から、コンテンツやメディアの未来像、私たちがどのように対応すればいいのか、そのヒントを探ります。
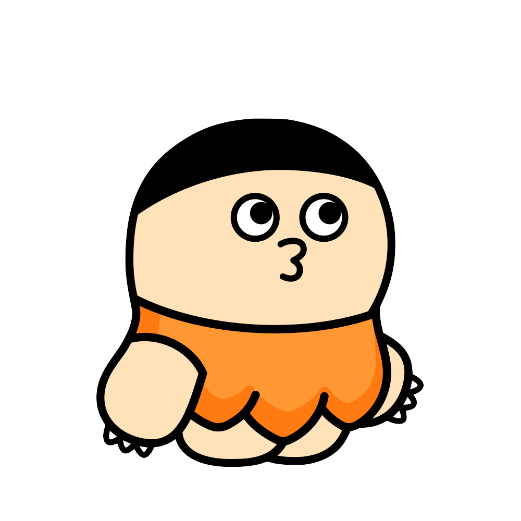
株式会社の仕組みや給与、スキルの常識が少しずつ壊れはじめている
――けんすうさんはWeb3やNFTを使ったビジネスをされていますが、こうした新しい技術領域で現在起こりつつある変化をどのように捉えていますか?
Web3は、インターネットの中にネイティブ通貨が生まれたと捉えています。あらゆる企業や個人が、通貨のようなものを作って取引できるようになった。そこは革命的ですね。
Web3はコミュニティや経済圏を作りやすいという特徴があります。例えば、僕のYouTubeチャンネルの書き起こしやサムネイルを作ってくれるのは、すべてWeb3上のコミュニティにいる人なんです。
しかも作った人に対して、コミュニティ内で「あなたはいい働きをしてくれるから、このコミュニティで使える100トークンをあげるよ」なんてことが起きている。しかも、僕が払っているわけではなく、コミュニティ内のメンバー同士がトークンで謝礼を払っているんです。そういう状態なので、もし僕のYouTubeチャンネルが盛り上がったら、トークンの価値が上がるからみんな嬉しい。もはや雇用の概念とは異なる世界になっているんですね。
実際にやってみると、株式会社を作って人を雇ってソフトやデザインを作ってもらうことは面倒です。それに比べると、コミュニティを使って自律的に作ってもらった方が楽だな、と。株式会社の仕組みや給与、スキルなどの常識が少しずつ壊れている気がします。
――Web3による新しい経済圏やコミュニティの誕生はこれから目を離すべきではない領域ですね。ところで、けんすうさんはAIもフル活用しているそうですが、今後AIは社会や経済に対してどのような影響を及ぼすと思われますか?
生成AIによって、産業革命やインターネットの出現に匹敵するレベルの変化があるだろうと思っています。産業革命では「人間が自分で歩かなくて済む」「服を手で縫わなくていい」といった変化がありました。今後は、「考える」という領域で同じようなことが起こるのではないか、と。
つまり、人間の脳みそだけでやっていたことを、これからはAIもできるようになる。人間が考えることは、東京から大阪まで行く時に「新幹線に乗る」のではなく、「歩いて行く」のと同じような扱いになるのではないでしょうか。
その結果、今まであった職人芸やギルドの仕組みだけでなく、働き方も人生設計も全部変わってしまうぐらいのことが起こるのではないかと思います。
――AIがさらに進化していくことで、私たちの仕事はどのように変化していくと予想していますか?
農業やものづくりは分かりませんが、基本的には給与が高いホワイトカラーからAIに置き換わっていくと思います。うちのエンジニアも、去年までは普通にコードを書いていましたが、いまはAIがやってくれるので、仕事のほとんどがAIへの指示やチェックになっています。
例えば、「新規のコミュニティを作りたい」というご相談を受けたとき、以前はリスク管理表やガイドラインの作成、運用方針など20時間ぐらいかけて作業をしていました。ところが、AIを使ったら5分ぐらいで出力され、最終チェックだけで済みましたからね。
――AIを使いこなせない人は、やはり仕事が減ってしまうのでしょうか?
例えば、ちょっとしたイラストであればAIが上手に描いてくれるので、イラストの発注は確実に減っています。そもそも1~2万円のような単発の依頼だと発注作業自体が面倒くさいし、人間は遅い。AIが1分で出力すれば、10回リテイクしても10分で終わるので、こっちの方がいいよね、となるでしょう。
ただ、翻訳家に話を聞くと、「仕事がゼロになりました」という人がいる一方で、仕事が10倍になっている人もいます。つまり、AIで仕事を効率化して請け負える仕事の量を増やした人が、それ以外の人の仕事を奪っているんです。
ある調査では超知能の誕生が2028年と言われているので、失業者が大量に出るのはそのあたりではないでしょうか。その頃にはAIが身体を持つ、つまりロボットになると予測されています。ただ、2028年だとそういうロボットは毎月100万台ぐらいしか作れないそうですが。
とはいえ、2029~2030年ごろまでにロボット経済がさらに進むとすると、今のような仕事があるのはあと5年くらいかもしれません。
――逆に、新しい仕事や産業が生まれてくる可能性はありますか?
考え方がガラリと変わることはあると思います。例えば、名刺って一度作ったらしばらく変えないですよね。でも、AI時代においては、会う人ごとに名刺を変えるかもしれません。
企業のロゴを作っていたデザイナーの仕事がなくなっても、「企業ロゴを毎月変える」みたいな状況になれば、AIを使いこなせる人が必要になるでしょう。LINEスタンプも、会話の流れに合わせて画像を生成して送れる機能が登場しています。「その都度、新しく○○を生成する」みたいな仕事が新しいスタイルになりそうですね。

ビデオポッドキャストが注目されている理由は、プラットフォームへの依存度が低いから
――AIはクリエイターやコンテンツにどんな影響を与えていくのでしょうか?
僕の例でいうと、自分でウェブサイトを検索して読むより、AIに作ってもらったレポートを読んでいる時間のほうが長くなっています。「○○の軸でまとめた××のレポートが読みたい」と指示すれば、AIが出力してくれるので。
コンテンツの中身をAIが作ってくれる時代においては、「誰がどう表現するか」がより重要になってくる気がします。例えば、アイドルや芸人さんがAIに話す内容を考えてもらって、それをその人のスタイルでしゃべる。
表現力がない人は、普通に発信しても見てもらえなくなるでしょう。エンタメコンテンツだと、「この芸人さんが悪口を言っているからこそ面白い」みたいな、UIとしての「人」が重要なので。
あとは、個人の発信者がいよいよ強くなるかな、と。僕の周りでは多くの経営者が、2025年からYouTubeを始めているんです。コンテンツをつくるとわかるのですが、とにかく中身が足りない。なので、まずは自分が考えたことや気づいたことをYouTubeとして外に出しているんです。さらに、切り抜き動画として拡散されることも見えていますから。
――クリエイティブやエンタテインメントコンテンツは、より細分化されて広がりにくくなるのでしょうか?
確かに細分化は進むので、「みんながこれを見ている」というのはあんまり起こらなくなるかな、と。どちらかといえば、「深さ」がより重要になるでしょうね。例えば、テレビ番組でよく行われているような一般向けイベントで多く人を集めるのは大変だけど、オードリーのラジオイベントだと東京ドームが満員になる、みたいな現象はどんどん起こる気がします。
今は『令和ロマンのご様子』というポッドキャストが人気のようですが、会議室でスタッフ1人とマイク、パソコンがあれば録音できるし、それが普通のラジオ番組より影響度が高い。そういうコンテンツが増え続けるだろうと思います。
――個人の発信力が強くなるとすると、プラットフォームと個人の関係性も変わってくるのでしょうね。
いま海外ではビデオポッドキャストが注目されています。その理由は、プラットフォームへの依存度が低いから。同じ番組をSpotifyやApple Musicなどで聞けるので、プラットフォームがおさえるというより、クリエイター側のほうが強いんですね。
YouTubeだとさすがにプラットフォーム側が圧倒的に強くて、BAN(アカウントが停止)されたり、アルゴリズムで出さなくなったりすると終わり、みたいなことが起こります。でも、ポッドキャストはそれが起きない仕組みになっています。
そのため、クリエイターはビデオポッドキャストを撮ってSpotifyやApple Music、X、TikTokなどいろんなところに出すようになるでしょう。

日本の強みは、編集者と漫画家の2人だけで世界的なIPを作れること
――「見る人によって映画の結末が変わる」など、AIによってコンテンツのパーソナライズ化が進むのではないか?という予測についてはどう思いますか?
うちの社員を例に考えていきます。彼はまず海外で出た面白そうな本を購入し、PDFでAIに読み込ませて日本語で図解させます。さらに、その内容を「AさんとBさんのポッドキャストで話しているふうにして」とAIに指示を出して音声を作り、それを聞いて勉強しているんです。
つまり、原書は英語のテキストですが、その人は図解を見ながら会話形式のポッドキャストを日本語で聞いて理解しようとしているわけです。もし難しい箇所があれば、「もうちょっと簡単に」とAIに指示して調整します。さらに、復習コンテンツとして動画化して勉強している。こういうことも普通になるでしょう。
また、うちの社内だと、AIがSlackのログを勝手に読み込むように設定していて、AIに「今のタスクは何?」と聞くと教えてくれます。AIの議事録とSlackのログから「これをやってください」と回答が出るし、ポッドキャスト形式でも聞けます。さらに、「ちょっと今のところ分からないんですけど……」というと、AIが返答してくれるんです。
おそらくニュースもそういう感じになるだろうな、と。ニュース動画を見ている途中に、「もうちょっと簡単に説明して」「関税ってそもそもなんですか?」と質問できれば、より理解度が高まりますよね。
そうなると、普通のアナウンサーが原稿を読むよりAIの方がいいよね、となるでしょう。「スタートアップ業界で例えるなら……」など、それぞれに合わせた具体例を提示させることもできるので、そっちの方が分かりやすいなと思いますね。
――話を少し変えますが、日本からフォートナイトやロブロックスのような世界・経済圏を持つプラットフォームが生まれる可能性はありますか?
アメリカと中国以外はかなり厳しいと思っています。ベンチャーキャピタルの投資金額で比較すると、アメリカは日本の100倍ぐらいあるし、エンジニアの人数やグローバルビジネスの経験者も桁違いなので。
ただ、プラットフォーム上で動くコンテンツでいえば日本はかなりすごいので、そこで勝負する方がいいんじゃないでしょうか。あとは、ゴーグルやロボティクスなど、ハードウェアと組み合わせられる企業ならチャンスがあるかもしれません。
日本の強みって、個人のクリエイターとプロデューサーの最小単位で作るものが面白い、という点だと解釈しています。漫画はそうですよね。『ONE PIECE』といった大ヒット作ですら、最近まで担当編集者は1人しかいなかったそうです。それなのに世界的なIPになっているわけですよね。
アメリカや中国は、大きなチームのマネジメントは得意だけど、個人プレーはそんなに得意ではないはずです。AI時代で「超スモールチームによる面白いもの」という勝負になると、日本にチャンスがあるのではないでしょうか。

ラジオは熱狂、雑誌はカルチャーや「深さ」を作っている
――AIが仕事内容を変質させていくとしたら、私たちはどう対応すればいいのでしょうか?
歴史を振り返ると、「必ず反対する人は出てくるけど、抵抗しても無駄」なので、さっさと新しいものに乗っていくほうがいいでしょう。エンジニアでいえば、「自分でコードを書かない前提で、ちょっと役割を変えなきゃ」と考える人は生き残りやすいと思います。
あとは、人間関係の価値はどんどん高まっていくでしょうね。誰に頼んでも料金が安くてクオリティが高くなるとすると、やっぱり人で探すようになるので。例えば、「この髪型にしてください」といえば、どの美容師さんも大抵できてしまいます。その結果、Instagramで「今日は○○を食べた」なども含めて個人としての発信が魅力的な美容師さんにお客さんが集まっているそうです。
結局、人に好かれるとか、飲み会に行って繋がりを作れる人が生き残るんだろうな、と思っています。
――テレビやラジオ、新聞、雑誌など、メディアの未来についてはどう思われますか?
企業の担当者と話していると、「トヨタイムズみたいなメディアを自社で持とう」みたいな流れが多いんです。テレビはそこと戦わなければなりません。
でも、ラジオを見ると「もうダメだ」と言われながらも、熱狂を作れるポイントを見つけてうまくいっている部分もある。なので、テレビも何か策があると思うんですよね。
雑誌は、逆に強いかも?と思っていて。雑誌は、カルチャーや「深さ」を作っているので、YouTubeに染み出たときに意外とうまくいっている、という話を聞きます。YouTubeと雑誌とECサイトの組み合わせは相性がすごく良いので、可能性があるかもしれません。
新聞は、もう少し別の形態になる可能性がありますね。例えば、10人のジャーナリズム集団がコンテンツを作り、みんなが課金する形はあるかなと思っています。ただ、真実に重要性を感じない人が増えているので、その点は危ういかもしれません。
――「真実が重要でない」という考え方について、けんすうさん自身はどう捉えていますか?
事実や真実と秩序がコンフリクトすると捉えています。トランプ大統領も、ウソをついていると思っている人が多いのにある意味許されている。政府には、事実よりも秩序が大事だと思っている人もいるからではないかと考えています。そういう手法が増えるとすると、新聞にとっては逆風かもしれません。
――おわりに――
事実と秩序のコンフリクトが起こっているとすると、ジャーナリズムにはそこから新たな価値を創出することが求められているのではないでしょうか。事実や真実を追求するだけでもなく、信じたいものを追求することで生みだそうとする秩序を重んじるだけでもなく、双方の側がどのような立場や感情からその価値観に基づいて行動しているのか、深く理解し、双方をつなぐことができるナラティブが必要なのかもしれません。
こうしたことは、テレビやラジオ、雑誌など、他のマスメディアにも今後必要ではないかと思われます。マスメディアが本来備えている、人々に寄り添い、その心を動かし、「情緒的な共感を生み出す力」や、そのための「コンテンツに深みを与える力」に改めて期待が集まっているように感じます。
逆に言えば、この「情緒的な共感を生み出す力」や「コンテンツに深みを与える力」こそ、新たなメディア環境におけるマスメディアの存在意義だと言えるのかもしれません。
けんすうさん、今日はどうもありがとうございました。
2025年4月10日インタビュー実施
聞き手:メディア環境研究所 冨永直基+所外協働プロジェクトメンバー 花光宣尚、鵜飼大幹
編集協力:村中貴士+有限会社ノオト
※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。

